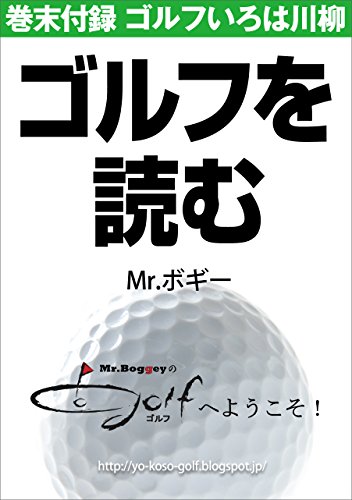ゴルフは紛れもなくスポーツにカテゴライズされるが、そこに知的ゲーム性の高いという形容詞を付けると、より正しく伝わるのではないか。知的ゲーム性の高いスポーツ、ボールゲーム、それがゴルフ。
1ラウンド5時間弱でラウンドする時、実際にスイングに要する時間はせいぜい20~30分程度である。残り約4時間半は、五感を働かせながら歩き、情報を収集し、その情報を分析し、次打の行動指針を決定する時間である。これはまるで情報処理。ゴルフはまさに頭脳戦。
ゴルフに必要なのは、ある程度の腕力、人並みの脚力、そして豊かな観察力、深い思考力、強い精神力。フィジカルスポーツではなく、メンタルスポーツ、それがゴルフ。
身体の構え以上に心の構えが大事なのが、メンタルスポーツであるゴルフ。ゴルフには、地のハザード、空のハザード、そして自分で自分にかけるプレッシャー、メンタルハザードがある。なかでも、あらゆる場面で現れるのがメンタルハザード。ゴルフはまさしく心理戦。
ゴルフ、このボールゲーム、まさしくコンピューターの情報処理の如し。
入力・分析(270分)+ 出力(30分)= ラウンド時間(300分)
入力・分析とは、五感を働かせながら歩き、情報を収集し、その情報を分析し、次打の行動指針を決定することである。準備に9割の時間を割き、実際のスウィング、ストロークに使う時間は1割。
ビギナー、初級者が初めに取り組むべきは、すさまじい球数を打ち込むことではなく、ゴルフの本質を知ることだろう。ラウンドの9割を占める時間をどう過ごすかで、スコアは必ず良くなるはずである。
早くボールを打ちたい、早くコースに出たい気持ちは分かるが、その前にすべきことがある。「肩や腰」の回転を熱心に研究するのもいいが、まずは「頭」の回転をゴルフ仕様にすることから始めてみてはどうだろう。
「ゴルフが難しいのは
プレーヤーが静止するボールを前にして、
これをいかに打たなければならないかについて、
考える時間があまりにも多いことに起因する」
(アーチー・ホバネシアン)
プレーヤーは、距離感、方向性などを惑すコースが用意した罠を見抜き、五感をフル回転させ風を感じ、傾斜を感じながら、様々な情報を収集。次にこの情報を分析、判断する。
ここから先はプレーヤーの個性と技量が表れるところで、攻めるもゴルフ、守るもゴルフ、飛ばすもゴルフ、飛ばさないのもゴルフ。ティから戦略を練るのもゴルフ、ピンから戦略を練るのもゴルフ。
ショットの成否によるもの以上に、あの時ああしておけばよかった、こうしておけばよかったなど、戦略の失敗、判断のミスを悔いるものが多いことに気付く。「過ちて改めざる 是を過ちと謂う」というが、ゴルファーは懲りない、何度やっても同じミスを繰り返す。だからゴルフは面白い。
「ゴルフは、体力よりも耳と耳の間にあるものでプレーされるゲームである」 (球聖 ボビー・ジョーンズ)
彼が言いたかったのは、ゴルフは腕力、脚力、腹背筋など筋力、体力もさることながら、それ以上に、脳力、五感を活かしてプレーしていくボールゲームである、ということだろう。やっぱりゴルフは、頭脳戦
自分に対する過大評価、強欲は自滅への誘い水となる。ホールアウト後の反省会、なるべく「タラ・レバ」は少なくしたいものだが、ラウンドの度に多くのタラ・レバに出会う。
特に、ショットの成否によるもの以上に、あの時ああしておけばよかった、こうしておけばよかったなど、戦略の失敗、判断のミスを悔いるものが多いことに気付く。
ゴルファーは、自分を過大に評価しがちである。クラブの飛距離を過大評価するため、グリーンに乗らず、ショートする。そのたびに首をかしげる。「絵に描いた餅」の連続は、根拠のない過信の証し。たいていの人は、自分はもっと飛ぶ、もっと上手いと思っている。実はこれがスコアメイクを難しくする。ゴルフを難しくする。
「ちょっとした見栄が、ゲームを台無しにする」 (プロゴルファー アーノルド・パーマー)
1926年全英オープン予選第2ラウンド、パー72でのボビー・ジョーンズの6アンダーの66というスコア。
スコア66 = アウト33+イン33 = ショット33+パット33
このスコア、実に美しい。
美しいだけではなく、ショートホール、ミドルホール、ロングホールの各スコアには、ある特徴があった。「ショートはすべてパー。ロングはすべてバーディ。ミドルはパーとバーディ」であった。ここにショート、ミドル、ロングそれぞれの攻め方のヒントがありそうだ。
当然のことながら、アマチュアゴルファーはこのセオリーでゴルフはできないが、どうプレーすればいいかのヒントにはなる。つまり、「ショートは守り、ロングは攻め、ミドルは守る・攻めるなどメリハリを効かせる」は、我々がやるゴルフのヒントにもなる。ただスコア設定が変わるだけである。